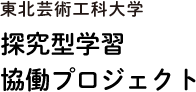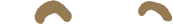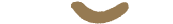2025.09.19
11/29[土] 探究型学習研究大会2025を開催!
大会テーマ|探究を軸としたこれからの学力観とその展望
東北芸術工科大学では、11月29日(土)に、全国の教育関係者・NPO・行政職員を対象とした探究型学習に関する全国大会「2025年度 探究型学習研究大会」を開催します。今年度も昨年と同様に、対面とオンラインの併用開催となりますので、皆様のご都合に合わせて、ご参集あるいはご参加をお願いいたします。
―はじめに―
「総合的な探究の時間」の全面実施から3年半が経ち、探究は学校教育において確かな位置を占めるようになってきました。今後は、その蓄積を踏まえ、教科との往還を意識しながら、探究を軸に据えた学力観をいかに構築し、学校全体に広げていくかが課題となってきます。その実現の先には、生徒が真に「主体的に課題を発見し、仲間と協働し、社会と関わりながら学びを広げていく」姿があり、まさに新しい学力の在り方を展望するものと考えます。 探究型学習研究大会は、「主体的・対話的で深い学び」を実現するための知を共有する場として、例年300名を超える皆様にご参加いただいています。
―大会テーマとプログラム―
今年度の研究大会では「探究を軸としたこれからの学力観とその展望」をテーマとして、2校からの日頃の探究活動に係る実践報告および講演の構成で実施いたします。はじめに、宮城県宮城第一高等学校の會田憲之氏、山形県立東桜学館高等学校の紺野陽人氏より、両校での特徴ある探究活動の取り組みをご紹介いただきます。また、実践報告をしていただく高校より、探究活動の成果として生徒の皆さんによるプレゼンテーションを披露いただきます。本研究大会における生徒の発表は初の試みです。続いて、独立行政法人教職員支援機構理事長の荒瀬克己氏より「何のための探究か」と題してご講演をいただきます。
上記の講演、報告、生徒発表を通した本研究大会での出会いと対話が、参加者の皆様にとって新たな学力観を描き、持続可能な探究の実践へとつなげていく契機となりますことを祈念いたします。
―大会を通じて―
昨今の社会的危機を乗り越えるべく、生徒とともに失敗を怖れず新たな挑戦を通して、社会的価値を創り出していく姿勢が「探究」に求められています。予測困難なこれからの時代に向けて、探究的、創造的な学びを引き出し、持続させるための糸口を各校に持ち帰っていただき、共有、展開していただけましたら幸いです。
―開催概要―
日 時 : 2025年11月29日(土)13:00~17:45(開場・開室12:30)
方 式 : ①対面(会場:東北芸術工科大学/山形市上桜田3-4-5)
方 式 : ②オンライン(Zoomによるライブ配信)
対 象 : 中学・高校教員、教育・NPO・自治体関係者
定 員 : 対面 100名/オンライン 250名 ※事前申込制
参加費 : 無料(事前申込制)
主 催 : 東北芸術工科大学
後 援 : 山形県教育委員会・山形市教育委員会・宮城県教育委員会・青森県教育委員会・秋田県教育委員会・岩手県教育委員会・福島県教育委員会
〈お申し込み方法〉
以下の申込フォームよりお申込みください。
【https://forms.gle/FPq6zTMyBxY7qeZp6】
※申し込み〆切:2025年11月21日(金)
※定員になり次第締め切らせていただきます。
※お申し込み受付後、参加に係る詳細をご連絡いたします
〈日程が合わず参加が難しい方〉
参加ご希望の方で、日程の都合で参加が難しいという方は、末尾に記載の担当者までご相談ください。
―プログラム―
—————————————
12:30~ 開場・Zoom開室
—————————————
13:00~ 開会挨拶
—————————————
13:10~14:20 実践報告1
「探究科の設置と普通科への広がり」
報告:會田 憲之(宮城県宮城第一高等学校)
※生徒による探究成果発表を含む
2022年度、本校では「国際探究科・理数探究科」を新設しました。探究科独自のプログラムを走らせるとともに、普通科の「総合的な探究の時間」の企画・運営にも取り組んできました。多くの外部人材の活用や教員研修を通じて探究への理解を深め、生徒・教職員の意識を育みながら進め、昨年には探究科第1期生を送り出しました。本報告では、その歩みを振り返り、成果と今後の展望についてお話しいたします。
—————————————
14:20~14:30 休憩
—————————————
14:30~15:40 実践報告2
「未来創造プロジェクト ~INPUTからOUTPUTへの試行錯誤~」
報告:紺野 陽人(山形県立東桜学館高等学校 )
※生徒による探究成果発表を含む
本校は開校して10年目。開校当初から「未来創造プロジェクト」と称して取り組んできた探究活動について、リサーチクエスチョン(研究テーマ)設定や探究活動の取り組み事例、外部団体との連携などについてご紹介いたします。また、課題研究における失敗例など、明確な指導法がない探究活動について皆様と悩みを共有していきたいと思います。
—————————————
15:40~15:50 休憩
—————————————
15:50~17:30 講演
「何のための探究か」
講師:荒瀬 克己(独立行政法人 教職員支援機構 理事長)
中教審・新しい時代の高等学校教育の在り方WGの「審議まとめ」(2020年)に、「生徒を主語にした高等学校教育」と記述されています。そのためには、どんなことが必要でしょう。問いが浮かびます。生徒は自分の疑問や興味・関心に基づいて探求しているか。社会の中で自分の役割を果たしながら自分らしく生きていくためにはどうするか。学校で、スクール・ポリシーは具現化しているか。ぜひご一緒に考えたいと思っています。
—————————————
17:35 閉会・諸連絡(17:45終了)
—————————————
―講師プロフィール―
荒瀬 克己|Arase Katsumi
独立行政法人 教職員支援機構
理事長
京都市立堀川高等学校校長、京都市教育委員会教育企画監を務めた後、大谷大学文学部教授、関西国際大学学長補佐を経て現職。独立行政法人国立高等専門学校機構監事、兵庫教育大学理事を兼職。前中央教育審議会会長。初等中等教育分科会長、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会長、高等学校教育の在り方ワーキンググループ主査や、義務教育の在り方ワーキンググループ、教育課程部会、教員養成部会等の委員等を歴任。
著書に『奇跡と呼ばれた学校』(朝日新書)、『「アクティブ・ラーニング」を考える』(共著、東洋館出版社)他。「月刊高校教育」(学事出版)にコラムを連載。
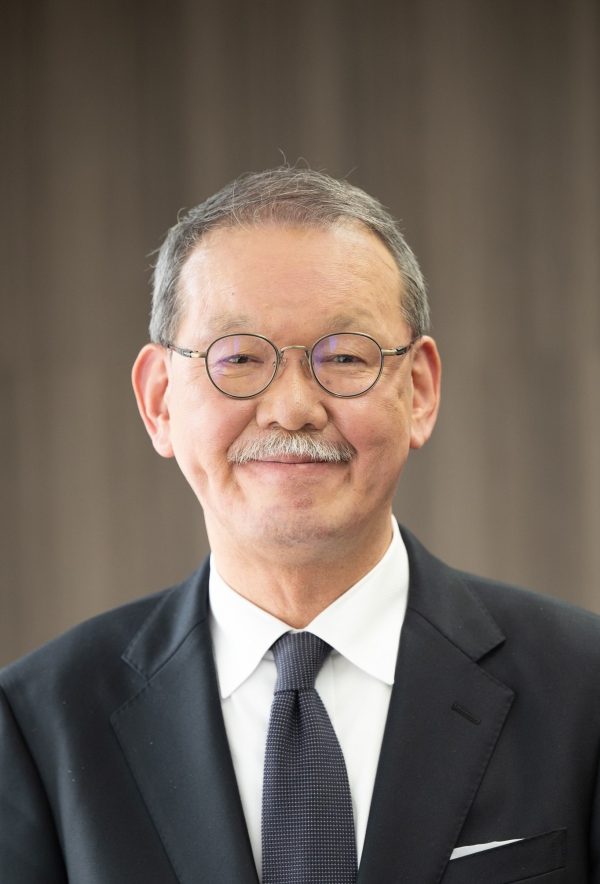
—————————————
會田 憲之 | Kaita Noriyuki
宮城県宮城第一高等学校 主幹教諭
令和3年度より宮城第一高等学校に主幹教諭として赴任。翌年度に控えた、宮城県内唯一の国際探究科・理数探究科の開科に向け、校内研修の企画、広報活動、新たな取組の校内調整などに携わる。普通科では1単位、探究科では2単位の「探究の時間」において、同僚と協働し、創意工夫を重ねながら企画・運営に取り組み、令和6年度に第1期生を送り出した。現在は国際理数部長も兼務し、持続可能で全校的な探究の質の向上に努めている。
—————————————
紺野 陽人 | Konno Hiroto
山形県立東桜学館高等学校 教諭
平成30年度に山形県立東桜学館高等学校へ赴任。令和5年度より、文部科学省指定「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」の事業に携わる研究課(校務分掌の一つ)に所属。生徒の課題研究全般の企画・運営・各種指導や外部機関との渉外を担当。本校では全職員体制で課題研究指導を行っており、より良い課題研究を行うためのシステム構築を模索している。
—————————————
■開催要項ダウンロード■
※近日中にアップいたしますので、少々お待ちくださいませ。
■大会コーディネーター■
柚木 泰彦(東北芸術工科大学 高大連携推進部長/プロダクトデザイン学科 教授)
青栁 敦子(同大 教職課程 教授)
吉田 卓哉(同大 教職課程 教授)
工藤 優太(同大 地域連携推進課)
■本件に関するお問い合わせ先■
東北芸術工科大学 地域連携推進課(担当:工藤優太)
〒990-9530 山形県山形市上桜田3-4-5
TEL:023-627-2139 FAX:023-627-2081(平日9:00~17:15)
E-mail:y-gakusha@aga.tuad.ac.jp